企業におけるSDGs・サステナビリティの取り組み~製造業編~
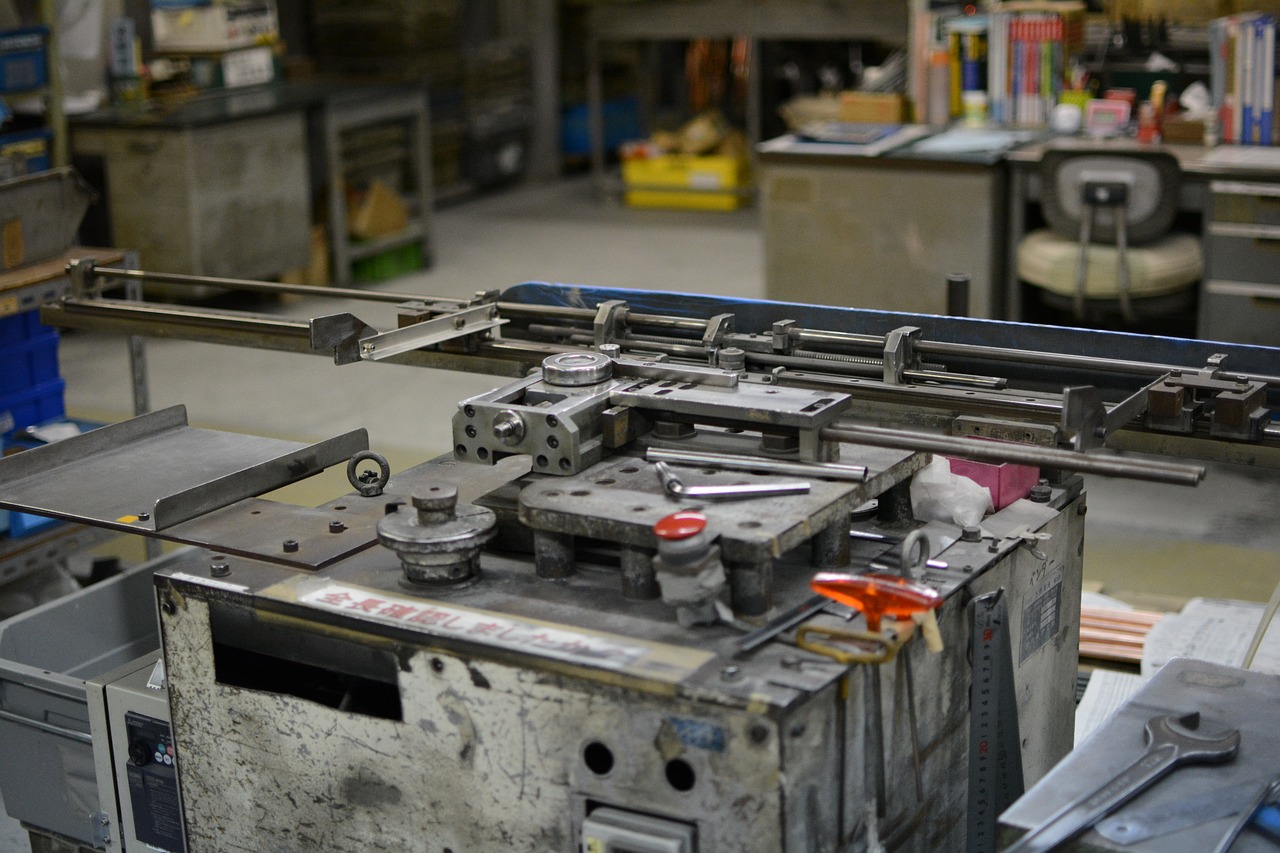
はじめに なぜ今、製造業にSDGsが求められているのか
近年、ビジネスの現場でもよく耳にするようになった「SDGs(持続可能な開発目標)」。
これは2015年に国連で採択された、2030年までに達成すべき17の目標です。貧困、教育、ジェンダー平等、気候変動など幅広いテーマが掲げられており、国や自治体だけでなく、企業にも積極的な関与が求められています。
中でも製造業は、環境への影響やエネルギー消費が大きく、サプライチェーンの起点にもなる業種であることから、SDGs達成において重要な役割を担っています。
さらに、脱炭素社会に向けた「カーボンニュートラル」や「グリーントランスフォーメーション(GX)」といった世界的な潮流もあり、製造業にはかつてない変革が求められています。
こうした時代の要請に応えるべく、今、製造業がSDGsに真剣に向き合う必要性が高まっています。
製造業に深く関わるSDGsの目標とは?
SDGsは全部で17の目標がありますが、製造業と特に関係が深いのは以下の4つです。
ゴール7:エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
製造業では膨大なエネルギーが使用されており、再生可能エネルギーの導入や省エネ化は喫緊の課題です。
ゴール9:産業と技術革新の基盤をつくろう
技術革新こそが製造業の本質であり、効率的で持続可能な生産技術の導入や、新素材の開発がSDGsの目標と一致します。
ゴール12:つくる責任、つかう責任
製品のライフサイクルを通じての責任ある生産、廃棄物の削減や循環型のものづくりが求められています。
ゴール13:気候変動に具体的な対策を
温室効果ガスの排出量削減は全産業共通のテーマですが、特に排出量の多い製造業は重要なプレイヤーです。
製造業が実践すべきSDGsの主要テーマ
製造業におけるSDGsの主要テーマについて確認しましょう。ものづくりの現場から調達先、職場環境の整備や地域貢献までさまざまな場面での取り組みが求められています。
1. 再生可能エネルギーの導入と省エネルギー化
製造業はさまざまな業種の中でも特にエネルギー消費量が多く、化石燃料依存からの脱却が急務です。
太陽光・風力・バイオマスといった再生可能エネルギーの導入は、脱炭素化と同時にエネルギーコストの長期的削減にもつながります。
加えて、工場内の高効率設備(インバータ制御機器、エネルギーマネジメントシステム等)への更新や、断熱・遮熱材の導入による空調負荷の軽減も、持続可能な経営に直結する施策です。
【取り組み例】
工場屋根への太陽光パネル設置/省エネ機器への切り替え/IoTでの電力管理
2. CO₂排出量の「見える化」と削減目標の設定
GHG(温室効果ガス)の削減は、Scope1(直接排出)/Scope2(間接排出)/Scope3(サプライチェーン全体)を意識して管理する必要があります。
SDGsへの取り組みを進める企業では脱炭素に向けてロードマップを策定し、2030年・2050年などの長期目標を掲げています。
AI・IoTを活用し、排出源を詳細にモニタリング・可視化することで、定量的な管理と定期的な改善PDCAが可能になります。
【取り組み例】
カーボンフットプリントの計測/非化石証書、グリーン電力証書/GHGプロトコルの導入
<参考>
環境省「サプライチェーン排出量算定について」
3. 廃棄物削減と循環型のものづくり(サーキュラーエコノミー)
SDGsの「つくる責任・つかう責任」に直結する分野です。
資源のロスをなくし、再利用・再資源化の仕組みを組み込んだ製品・プロセス設計が求められています。
製造過程で出る端材や不良品を再生原料に変えたり、リサイクルしやすい素材・接着剤・構造を製品に取り入れることで、廃棄物ゼロ=ゼロエミッション工場を目指す動きも広がっています。
【取り組み例】
製品設計段階からの「解体しやすさ」考慮/産廃からのエネルギー回収/再利用可能な素材の一元管理
4. サプライチェーン全体の持続可能性の向上
自社単体ではなく、バリューチェーン全体でのサステナビリティ管理が求められるようになっています。
「グリーン調達」「責任ある鉱物調達」など、調達先に対しても環境・人権・労働基準などの配慮が義務付けられる動きが世界的に進んでいます。
透明性を高めるために、トレーサビリティ管理や環境・人権・倫理を対象としたCSR監査の実施も今後重要になるでしょう。
【取り組み例】
CSR調達ガイドラインの整備/取引先への自己診断書の提出/RBA(Responsible Business Alliance)行動規範への準拠
5. 働きがいのある職場づくりと人権尊重
多様な人材が活躍できる環境を整えることも、SDGs達成の重要テーマです。
特に製造業では、技能実習生や高齢者、女性の現場進出をどう支えるかが課題となっており、労働時間・安全衛生・教育機会・ハラスメント対策などが焦点となります。
さらに、ジェンダー平等の推進、育児・介護との両立支援、障がい者雇用の推進なども社会的責任の一環として取り組むべき事項です。
【取り組み例】
ダイバーシティ研修/女性向け作業着の導入/エンゲージメント調査の実施
6. デジタル技術を活用した環境負荷の低減(スマートファクトリー)
IoT・AI・ロボティクスを活用することで、エネルギーの最適化・無駄の削減・品質安定化などが実現できます。
これにより、生産性と環境配慮を両立するスマートファクトリー化が進められています。
【取り組み例】
設備稼働の自動最適化/AIによる需要予測に基づく生産調整/AIによる歩留まり改善
7. 製品そのものの「環境配慮設計(エコデザイン)」
製品が市場に出てからも、長寿命・省エネ・再利用可能性の高い製品設計がSDGsに貢献します。
また、消費者のSDGs意識も高まっており、「環境に優しい製品」であることが差別化要素にもなっています。
【取り組み例】
再生材や生分解性プラスチックの活用/モジュール交換可能な製品構造/LCA(ライフサイクルアセスメント)の導入
8. 地域社会との共生と価値創出
地域に根ざした製造業は、地域資源の活用、雇用創出、地元教育機関との連携などを通じて、地域社会との共生も重要テーマです。
これはSDGsのゴール11「住み続けられるまちづくり」にも貢献します。
【取り組み例】
地域イベント・学校との連携プログラム/地産地消のものづくり/地域清掃・環境保全活動の支援
製造業におけるSDGs実践事例
具体的な実践例を見てみましょう。興味のある取り組みはリンク先で詳細を確認してみてください。
1. 水素エネルギー推進とWoven City(トヨタ自動車株式会社)
トヨタは、従来のEV戦略に加え、水素社会の構築にも注力しています。水素エンジン車の開発加速と水素インフラの整備支援を強化を進めるとともに、「Woven City」構想では、富士山麓の静岡県裾野市にてカーボンニュートラルな都市実証を行っており、再生可能エネルギーの地産地消、移動・物流のゼロエミッション化など、未来の都市づくりに挑戦しています。
<参考>
トヨタ サステナビリティサイト
Toyota Woven City
2. 輸送改善などによるCO₂削減(株式会社なとり)
おつまみ製品を主力とするなとりでは、輸送手段のモーダルシフト(鉄道コンテナの利用)によりCO₂排出量を大幅に削減し、環境配慮と物流効率の両立を実現しました。一例を挙げると、2024年4月よりチーズ鱈等の工場などからの輸送を鉄道化したことで、年間240トンのCO₂削減が図られています。
また、工場に太陽光発電設備を設置したことで、年間あたり約340トンのCO₂削減が図られています(埼玉第二工場)。
その他、製品のトレーを環境配慮型素材に変更、賞味期間の延長による食品ロス削減などにも取り組んでいます。
<参考>
なとり「SDGsへの取り組み」
3. 石油由来原材料の削減や再生可能エネルギー導入(雪ヶ谷化学工業株式会社)
雪ヶ谷化学工業株式会社は、化粧品用スポンジなどを製造する企業で、「雪ヶ谷サステナブルチャレンジ2030」を掲げ、SDGsに取り組んでいます。植物由来原料やフェアトレード天然ゴムの採用により、石油由来原材料の削減を進めるほか、つくば工場では再生可能エネルギーの導入により実質再生可能エネルギー比率100%を実現しています。また、2030年までに女性管理職比率50%を目指すなど、ジェンダー平等の推進にも注力しています。
<参考>
YUKIGAYA×SDGs
SDGsに取り組むことで得られる5つのメリット
製造業において、SDGsに取り組むメリットについて整理します。単に「環境に良いことをする」だけにとどまらず、事業・経営の根幹に直結する成果へとつながっていく、「SDGsに取り組むこと=企業価値を高めること」として捉える視点が、あらゆる規模・地域の製造業に求められます。
①ブランド力・企業価値の向上
SDGsに真摯に取り組む企業は、社会的信頼を得やすくなり、顧客・取引先・投資家などステークホルダーからの評価につながります。近年では、環境や人権に配慮した企業とそうでない企業とが、選ばれるか否かの分かれ目になることも珍しくありません。
特にBtoB領域では、サプライヤー選定時に「SDGs達成への姿勢」「CO₂排出量の見える化」「再エネ率」などがチェック項目に入るケースも増えています。
さらに、サステナビリティ関連の第三者評価を受けることで、企業の信用格付けにもプラス効果が期待できます。
②補助金・認証・調達での優遇対象となる可能性
環境・社会課題の解決に貢献する企業は、国や自治体からの各種補助金・助成金の対象となりやすくなります。
また、環境認証(ISO14001、エコアクション21など)やサプライチェーン調達認証(グリーン調達、RBA準拠など)を取得することで、官公庁・大手企業との取引要件をクリアできるケースもあります。
③若手人材の採用・定着
Z世代をはじめとした若手人材は、企業の社会的意義や共感できるビジョンを重視して就職先を選ぶ傾向があります。
実際に「就職先としてSDGsに取り組む企業を選びたい」と回答する学生は年々増加しており、大学・専門学校のキャリア支援でもSDGsに取り組む企業が積極的に紹介される例が見られます。
さらに、入社後も「社会に貢献できる職場」「誇りを持てる仕事」があることで、従業員のエンゲージメントや離職防止にもつながります。
④コスト削減・業務効率化の実現
SDGsへの取り組みは「コストがかかる」と思われがちですが、実は多くの場合、長期的には経費削減につながるケースが多くあります。
・工場のLED照明化 → 電気代の削減
・廃材の分別・再利用 → 産業廃棄物処理費の削減
・デジタル化による紙の使用量削減 → 印刷・保管コストの削減
また、エネルギー管理システム(EMS)やIoTによる設備稼働最適化により、業務効率と生産性の向上も見込めます。
単なる「社会貢献」ではなく、経営合理化の戦略としてSDGsを取り入れることが重要です。
⑤海外市場での競争力向上・リスクヘッジ
EUをはじめとする諸外国では、サプライチェーン全体の環境・人権・労働状況への開示義務が進んでおり、SDGsの取り組みがない企業は輸出や国際調達で不利になるケースが増えています。将来的なリスク回避の意味でも、今のうちから取り組むことは企業経営にとって重要と言えます。特にアパレル、電子機器、自動車など、グローバル供給網を持つ製造業ほど影響は大きいです。
SDGs推進の課題
SDGsの重要性を理解していても、実際に取り組みを進めるとなると、製造業特有の課題が立ちはだかります。ここでは、特に多くの企業が直面する代表的な3つの壁と、それぞれの対策をご紹介します。
①中小企業における資金・人材・ノウハウの不足
<課題>
製造業の多くを占める中小企業にとって、初期投資や人材確保がSDGs推進のボトルネックになります。
・再生可能エネルギー設備の導入はコストがかかりすぎる
・専任のSDGs推進担当がいない
・何から始めればいいか分からない
こうした声は現場でよく聞かれます。特に、日々の生産や納期対応に追われる中小企業では、「SDGsは余裕のある企業がやるもの」という誤解も少なくありません。
<対策>
1.小さなアクションから着手する
・工場内の照明のLED化
・廃材の分別やリユース
・近隣企業と共同での研修会開催 など
2.国や自治体、商工会議所の支援制度を活用
国の予算事業や地方自治体、商工会議所などによる助成金制度、支援制度を活用できる可能性があります。
<参考>
東京都・国のサステナビリティ補助金・助成金情報
②現場と経営層の間にある「意識のギャップ」
<課題>
経営層が「SDGsを経営戦略に取り入れたい」と考えても、現場にはその重要性が浸透していないケースは多々あります。
・現場の人は忙しくて、SDGsに割く時間がない
・単なるPR活動だと思っている
・自分の仕事とは関係ないと感じている
特にベテラン社員や製造現場の従業員は、変化に対する抵抗感を持ちやすい傾向があります。
<対策>
1.現場目線でのSDGs説明を行う
・廃棄物の削減=廃棄コストの削減
・設備の省エネ化=現場の快適さ向上
といった、現場のメリットに直結する言葉で語ることが重要です。
2.小さな成功事例を社内で共有
・LED化で○円のコスト削減
・廃材再利用で現場の工夫が評価された
など現場の成果を見える化・表彰し、モチベーションを高める
3.若手・現場リーダーをSDGs推進の担い手に育成
・社内研修・eラーニングの実施
③SDGsウォッシュ(見せかけの取り組み)への懸念
<課題>
SDGsという言葉が広まる一方で、実態が伴わない「見せかけのSDGs」=SDGsウォッシュが問題視されています。
・実質的な取り組みがないのに「SDGsやってます」と掲げる
・本業と関係のない活動ばかりを強調する
・定量的な目標や評価基準がない
度が過ぎれば取引先や消費者からの信頼を損なうリスクがあります。
<対策>
1.本業とSDGsの接点を明確にする
・自社の製造技術で環境負荷をどう下げられるか
・どのSDGsゴールと自社の取り組みが結びつくか
を明文化し、社内外に発信する。
2.KPI(数値目標)とPDCAを設ける
・2026年までに工場CO₂排出量を15%削減
・再生素材の使用率を年5%ずつ向上
など定量目標を持つことで、見せかけではなく成果で語る。
3.第三者認証・外部評価を活用する
・ISO14001やEcoVadisなどの認証取得
・外部機関からのアドバイス・監査導入も有効
今すぐ始める!製造業におけるSDGsアクション例
SDGsは「大きな目標」ではありますが、毎日の製造現場の積み重ねの延長線上にあるものばかりです。
「完璧な計画」よりも、「一歩を踏み出すこと」が企業の価値を高め、社員や地域社会との関係も育てていきます。
「SDGsってよく分からないな…」という社員が多くても問題ありません。まずは「LED化」や「廃材分別の徹底」から始めてみることが第一歩になります。
ステップ①
●工場内の照明をLEDに切り替える
・既存の蛍光灯をLEDにすることで電力削減が可能
・環境負荷の低減と同時に、照度が安定して作業効率や安全性も向上
【SDGsゴール】7(エネルギー)、13(気候変動)
●廃材・端材を分類・活用する仕組みを見直す
・金属くず、木材の端材、梱包材などの素材ごとの分別を徹底
・リユース・再利用のルートを構築し、廃棄コストを削減できるケースも
【SDGsゴール】12(つくる責任 つかう責任)
●社員のマイボトル・マイ箸推奨
・工場や休憩所のペットボトル・割り箸の使用削減
・ノベルティとしてオリジナルマイボトルを配布する企業も
【SDGsゴール】12(つくる責任 つかう責任)、14(海の豊かさ)
●社内掲示板や社報でSDGsを「見える化」する
・「SDGsとは?」から始まり、自社の取り組みや目標を視覚的に掲示
・ロゴやピクトグラムを使うことで、視覚的な関心と浸透が促進
【SDGsゴール】4(教育)、17(パートナーシップ)
ステップ②
●廃棄工程を見直し、「ゼロエミッション」化へ
・廃棄物の再資源化率を測定し、ゼロエミッションに近づける計画を立案
・排出業者との連携で、有価物取引の可能性もある
【SDGsゴール】9(産業と技術革新)、12(つくる責任 つかう責任)
●エネルギー使用量を「見える化」する
・スマートメーターやエネルギー管理システム(EMS)を導入し、電力・燃料消費を可視化
・ピーク時間のシフトや省エネ機器への切り替え判断にも活用可能
【SDGsゴール】7(エネルギー)、13(気候変動)
●SDGsを意識した製品・技術開発
・「リサイクル可能な部品構造」「分解しやすいパッケージ」「省エネ設計」など
・顧客からの評価アップや差別化にもつながる
【SDGsゴール】】9(産業と技術革新)、12(つくる責任 つかう責任)、13(気候変動)
●地域・取引先と連携した「清掃活動・啓発活動」
・周辺道路や工場周辺での清掃活動・グリーンカーテンの設置
・地域の学校や取引先と「環境の日」を設けて共同アクションを実施
【SDGsゴール】11(まちづくり)、17(パートナーシップ)
ステップ③
●社内に「SDGs推進チーム」や「サステナビリティ委員会」を設置
・経営層と現場をつなぐハブとして、社内横断的なプロジェクトチームを編成
・年間計画やKPI設定、社内発表会などを通じて主体性を育む
【SDGsゴール】17(パートナーシップ)
●外部認証を取得する(ISO14001、エコアクション21など)
・環境マネジメント体制を整備し、対外的な信頼性を向上
・認証取得により、入札参加資格や取引先選定条件を満たせる場合も
【SDGsゴール】12(つくる責任 つかう責任)、13(気候変動)
●社員向けの「SDGs教育・eラーニング」導入
・若手〜ベテランまでを対象に、役職・現場別の教育カリキュラムを整備
・特に製造現場のリーダー層を巻き込むことで、実行段階まで浸透
【SDGsゴール】4(教育)、8(働きがい)
●サプライチェーン全体に「CSR調達ガイドライン」を展開
・協力会社・仕入先にもSDGsやESGへの理解を求める
・グリーン調達、責任ある鉱物調達、労働環境のチェック体制を導入
【SDGsゴール】8(働きがい)、12(つくる責任 つかう責任)、17(パートナーシップ)
まとめ
持続可能な社会を実現するために、製造業が果たすべき役割はかつてないほど大きくなっています。
エネルギー、資源、人材、地域、そして技術――あらゆる面で社会と密接に関わる製造業は、SDGsの実現における現場の最前線です。
SDGsに取り組むことで得られるのは、単なる社会的評価だけではありません。
ブランド力の向上、補助金や取引先との連携強化、若手人材の確保、コスト削減、海外競争力の強化など、企業経営そのものを強くする戦略的な効果も見込めます。
「何から始めればいいかわからない」「うちのような中小企業には難しい」と感じる企業も多いと思いますが、今回ご紹介したように、廃材の分別やLED化といった小さなアクションでも、立派なSDGsの第一歩です。
また、社内の意識改革やKPIの設定、外部連携などを通じて、SDGsを企業文化に根付かせていくプロセスも、長期的に価値ある財産となります。
Sus&Us編集部

